テニス選手の大坂なおみさんが注目を集めておりますね。
大坂さんは日本国籍をお持ちですが日本語があまり話せておりませんね。
なぜ大坂さんは日本語を少ししか話せないのでしょうか?
今回はその理由について調査を進めてていこうと思います。
最後までお願いします(^^♪
大坂なおみはなぜ日本語を少ししか話せない?
日本にいた期間は短い
大坂なおみさんが日本語を流暢に話せない理由の一つに、日本に住んでいた期間の短さがあります。
彼女は大阪府大阪市で生まれましたが、わずか3〜4歳の時に家族と共にアメリカへ移住しています。
つまり、日本での生活はほんの数年しかなく、以後の人生はほぼアメリカで過ごしているのです。
家庭内でも英語中心で育ったため、当然ながら言語としての日本語を学ぶ機会は非常に限られていました。
さらに、彼女が育ったのは英語圏のフロリダ州であり、日常生活、学校、トレーニングなどあらゆる場面で使われる言語は英語が中心でした。
したがって、日本語に触れる環境がそもそも少なく、結果として今も「日本語は少し話せるけれど流暢ではない」という状況になっています。
実際、大坂選手が日本語を話すときには努力して言葉を選びながら話している様子が見られます。それは彼女の「不慣れさ」ではなく、環境的に自然なことなのです。
アメリカで英語中心の生活を送っていた
大坂なおみさんはアメリカでの生活が非常に長く、彼女の言語生活も当然英語が中心でした。
3歳で渡米して以降、彼女は主に英語で教育を受け、テニスも英語で指導されてきました。
特に父親はハイチ出身で英語でのコミュニケーションが基本、母親も家庭内では英語を使っていたとされており、日本語を使用する機会は非常に限定的でした。
実際、彼女のインタビューを見ると、英語では非常にスムーズに話す一方、日本語になると少し時間をかけて言葉を選んだり、表現に詰まったりすることがあります。
これは「努力不足」では決してなく、彼女にとっては英語が日常言語であり、日本語は第二言語、もしくは「外国語に近い位置づけ」であることが関係しています。
大坂なおみの母国語は英語
日本国籍はあるが母国語は英語
大坂なおみさんは日本とアメリカの二重国籍として育ちました(22歳のときに日本国籍を選択)。
しかし、彼女にとっての「母国語」は明らかに英語です。
幼少期から現在に至るまで、教育、トレーニング、日常会話のすべてを英語で行ってきたため、思考も英語で行われています。
言語は単なるツールではなく、自分の感情や考えをもっとも自然に表現できる手段です。彼女にとって、それが英語なのは当然のことです。
日本人選手であっても、環境によっては「日本語を苦手に感じる」ということは珍しくありません。
大坂なおみさんの場合、彼女のルーツの一部が日本にあることは事実ですが、言語的には英語が圧倒的に優位です。
ですので、「日本人だから日本語ができて当たり前」という考え方は、彼女の歩んできた人生を無視した非常に表面的な見方と言えるでしょう。
インタビューなどは英語にすべき
実際に、2019年の全豪オープンで優勝した際、大坂選手は試合直後のインタビューで日本語での応答を拒否したことがあります。
これについては一部のメディアが批判的に報じましたが、実際は「英語の方が自分の気持ちを正確に表現できるから」というごく自然な理由によるものでした。
試合直後は感情が高ぶっている状態です。その中で、慣れていない日本語で無理に話すことは、本人にとってストレスになりますし、伝えたいことをうまく言葉にできない可能性もあります。
そんな状況で日本語でのコメントを強要するのは、選手への配慮に欠ける行動と言えるでしょう。
英語で話しても、それを通訳を通じて日本語で届けることは可能です。
選手の本音や感情をしっかり伝えることが何より大切であり、それが本人の自然な言語であるならば、インタビューも英語で行うべきです。
まとめ
今回は大坂なおみさんが日本語を少ししか話せない理由について調査をしていきました。
大坂なおみさんが日本語をうまく話せないのは、「怠けているから」でも「日本人らしくないから」でもありません。
彼女は3〜4歳でアメリカに移り住み、それ以来ずっと英語中心の環境で育ってきました。
日本語を「学ぶ機会」そのものが非常に限られていたため、英語が自然と母国語になったのです。
それでも、彼女は日本語を少しずつ覚え、試合後のインタビューなどでも日本語を使おうと努力している姿が見られます。
そのような姿勢こそ評価すべきであり、むしろ「カタコトでも話せる」ことを尊重すべきではないでしょうか。
日本のメディアやファンが彼女に対して理解を深め、無理に日本語で話すことを求めず、自然体でいられる環境を整えていくことが大切です。
日本国籍であることと日本語が得意であることはイコールではありません。
彼女の生い立ちや背景を踏まえた上で、敬意を持って接することが、今後の国際的なスポーツ文化にも求められる姿勢と言えるでしょう。
最後までありがとうございました(^^♪

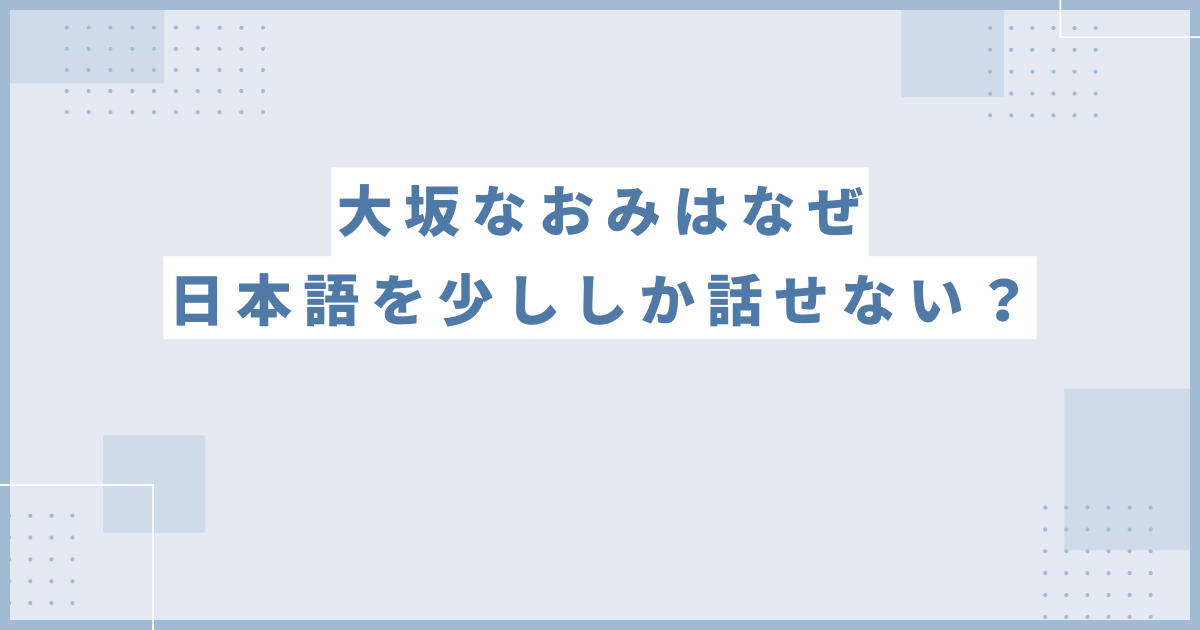
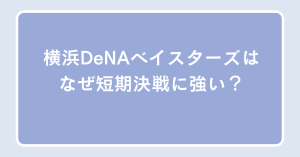
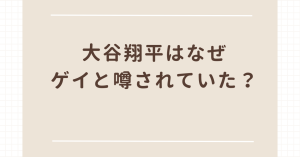
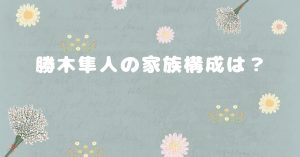
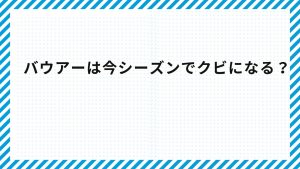
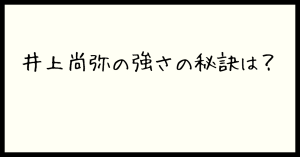
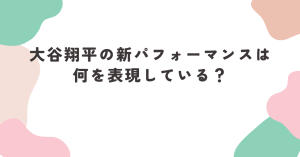
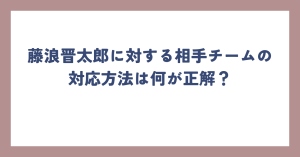
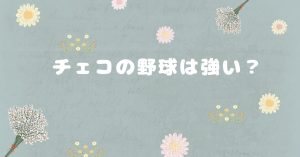
コメント