2025年のプロ野球シーズンも盛り上がりを見せておりますね。
そんな中で横浜DeNAベイスターズの打撃低迷が目立っております。
なぜ、2025年のベイスターズは打撃低迷しているのでしょうか?
今回はその原因について調査をしていこうと思います!
最後までお願いします(^^♪
横浜DeNAベイスターズの打撃低迷の原因はなぜ?
オースティン選手の離脱
タイラー・オースティンの離脱は、DeNAの打線にとって極めて大きな損失です。
昨季はセ・リーグ首位打者に輝き、OPSも驚異の.983をマーク。
得点力の核とも言える存在だったオースティンが不在となったことで、相手投手にプレッシャーを与える存在が減り、チーム全体の打撃バランスが大きく崩れるきっかけとなっていることは間違えありません。
特に、彼のような長打力のある打者がいなくなると、得点パターンの幅が狭まり、チャンスを得点に結びつける力が落ちてしまうのです。
宮崎選手の不調
昨季まで安定した成績を残してきた宮崎敏郎選手も、今季は大きく数字を落としています。
昨年は打率.283、OPS.815と中軸の役割を担っていましたが、今季は打率、OPSともに急落。
この数字はチームにとって想定外の誤算です。
宮崎選手のような勝負強い打者が不調に陥ると、得点機での打撃に期待がかけづらくなり、打線が線として繋がりにくくなってしまいます。
石井コーチの不在
打撃の再建を支えてきた名コーチ・石井琢朗氏の一軍帯同の不在も、打線の不調に拍車をかけています。
選手個人個人のバットを振る「準備」ができていない場面が目立つとの指摘もあり、技術よりも“気持ちの問題”が問われる場面が増えています。
チームがバラバラな方向を向いてしまい、打線としての一体感を欠いていることも、戦術・精神面の両面で石井コーチの存在感を物語っています。
活躍を期待されている若手選手の不調
若手選手の不調も低迷のきっかけになっております。
2024年の日本シリーズで活躍をした梶原選手、森選手、林選手はいずれも期待されたような成績を残すことができておらず首脳陣を大きく悩ますことになっております。
各選手一人一人が打線の中で自分の役割を理解し、実行する選手が少ないことが、得点力の低下につながっているといえるでしょう。
横浜DeNAベイスターズの復活へのカギは?
外国人選手が機能する
チームの得点源として期待される外国人選手、特にオースティンの復帰や新戦力の活躍は、打線の厚みを増すための重要なポイントです。
昨季のようにオースティンが中軸で機能すれば、相手投手の攻め方も変わり、他の打者の打撃機会も向上します。
外国人選手の復調は、打線全体の活性化に直結するでしょう。
他にもフォード選手やビシエド選手といった新加入の外国人選手の活躍にも期待が集まります!
石井コーチの1軍帯同
「打撃の準備ができていない」という現在の課題を解消するには、石井琢朗コーチの一軍復帰が有効と考えられます。
選手の技術的な指導はもちろん、精神面でのサポートにも定評がある石井コーチの指導力が、低迷打線を再び“線”として機能させるカギになるはずです。
石井コーチの指導を待っている選手も多いようですね。
不調選手の復調
宮崎敏郎選手、筒香嘉智選手など、本来であれば打線の中核を担うべき選手たちの調子が戻るかどうかが、チーム全体の浮沈を握っています。
数字を見ても、いずれも昨季よりも打率・OPSともに下がっており、これらの主力が自らの持ち味を取り戻せれば、得点力の回復は大いに見込めます。
そういった選手の復活こそ、最大のカギになりそうですね!
まとめ
今回は横浜DeNAベイスターズの打撃低迷の原因について調査をしていきました。
今季の横浜DeNAベイスターズの打撃不振は、オースティン選手の離脱をはじめとした主力の不在や不調、精神面での準備不足、若手の停滞など複合的な要因によって引き起こされています。
しかしながら、希望もあります。外国人選手の復帰、石井コーチの指導再開、主力の復調などが実現すれば、昨季のような強打のDeNA打線が戻ってくる可能性は十分にあります。
チーム全体が一丸となって、まずは目の前の1点に集中する戦い方が復活への近道と言えるでしょう。
後半戦の巻き返しに期待ですね!
最後までありがとうございました(^^♪

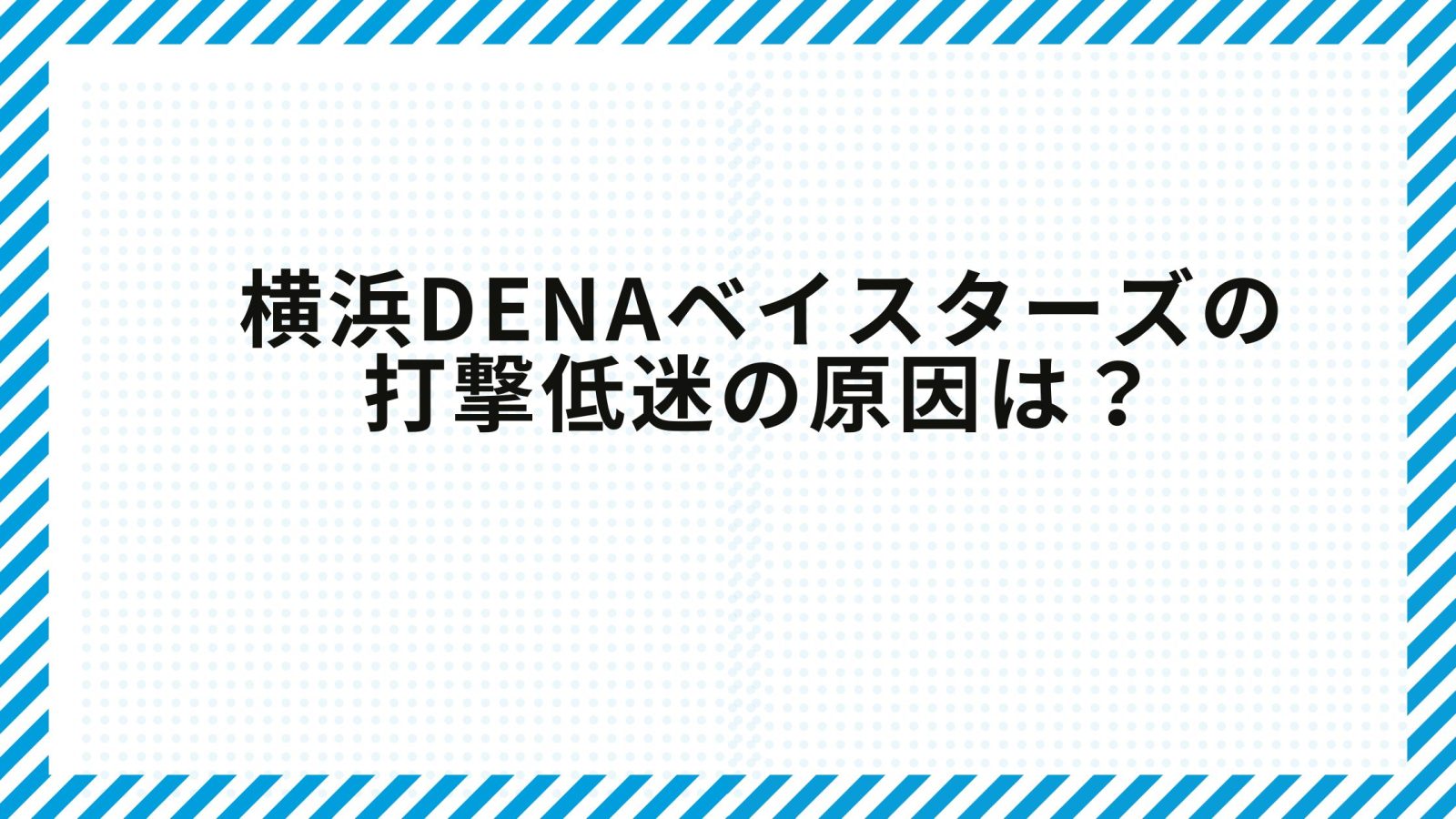
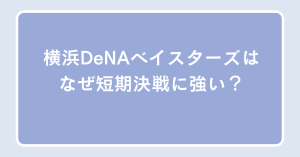
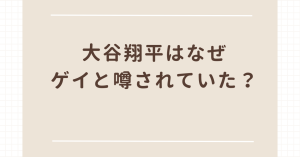
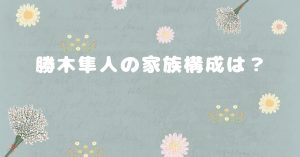
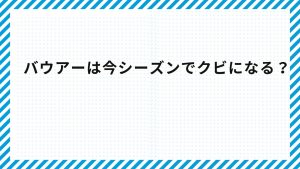
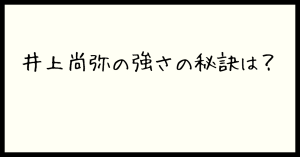
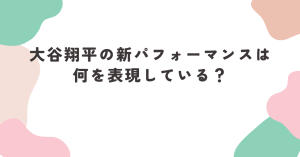
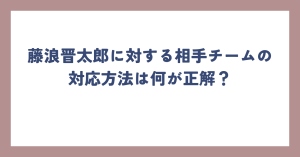
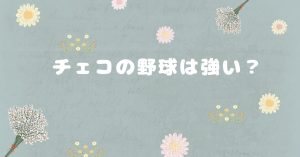
コメント